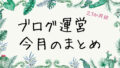我が家の長男は1歳から3歳まで2年4か月間、小規模保育園に通っていました。
そして3歳の3月に卒園し、4月から別の保育園に入園しました。
次男と3男は1歳から普通の認可保育園に通っています。
小規模保育園に入園が決まった時は、少し残念な気持ちもありましたが、実際に通ってみてよかったと思うことも色々あります。
そこで今回は、長男が通っていた保育園と、次男と3男が今通っている保育園を比較してよかったと思うこと(メリット)と残念だと思うこと(デメリット)をまとめたいと思います。
保育園を選ぶ際の参考にして頂ければ幸いです。
(注)保育園の年齢表示(0歳~5歳)は年度始め(4月)時点での年齢です。
小規模保育園のメリット
保育園ごとに方針などは全然違うので、あくまでも我が家が経験した保育園ではという話です。
①こどもの数が少なくアットホームな雰囲気
小規模保育園のメリットは、なんといってもこどもの数が全体的に少ないこと。
保育園に入園する前は家族の中で穏やかに生活していた小さなこどもが、突然家族から離れて保育園で大人数のこども達に囲まれて生活をし始めます。
環境が大きく変わります。
その環境の変化を上手に受け入れられる子もいれば苦手な子もいます。
我が家では長男も次男も環境の変化が苦手で、4月に入所した後、夏ごろまで毎朝保育園で泣いていました。
小規模保育園ではこどもの数が少なくアットホームな雰囲気なので、比較的馴染みやすくこどもが安心できる環境かなという印象です。
②こどもに対して先生の数が多く、色んな経験をさせてくれる
保育園にもよりますが、小規模保育園の方がこどもの数に対して先生の数が多い印象です。
なので一人一人を丁寧に見てくれます。
そして小規模だからやり易いのか、リトミック、体操、英語など外部の先生が定期的に来て、色んな経験をさせてくれました。
また、朝の会でフラッシュカードのようにカードを使って国旗や漢字を覚えたりもしていました。
1歳や2歳の長男が「インドネシア」「カンボジア」「フランス」など、色んな国旗を覚えていて、もうこんなことができるんだと驚きました。
その時に国旗カルタや国旗の本を買い、小学1年生になった今でも国旗カルタで遊んだり本を読んだりしているので国旗をよく覚えています。
こどもの能力をたくさん引き出してもらい、いい経験をさせてもらったと今でも感謝しています。
③玄関で荷物とこどもを引き取ってくれるので朝の保育園滞在時間が短い
小規模保育園を卒園して、今の保育園に通い始めて一番最初に思ったのが、毎朝保育園での準備をするのが大変だということです。
小規模保育園では朝、保育園の玄関へ先生が来てくれてこどもと荷物を渡して連絡事項を伝えるだけで、保育園の中での準備などは全て先生がしてくれました。
そしてこどもが泣いていても、カッパや上着を脱がないとグズっても、そのまま抱っこで預かってもらうことができました。
今の保育園では、親が部屋の中まで入って、こどもと一緒に荷物の準備をして体温を測り、トイレを済ませ、手洗いをして初めて受け入れしてくれます。
こどもを預けるのだから、その準備を親がするのは当然なのですが、小規模保育園はとても楽だったと今になって痛感しています。
そして、今の保育園でも、こどもが泣いていてもそのまま抱っこで預かってもらえるのですが、時間によっては大人数のこども達を一人の先生で見ている時間などもあり、大泣きして保育室に入るのを嫌がっている状態で引き渡すのが申し訳なく、保育室の前で親が抱っこしたり話をして落ち着かせたりしています。
少し待っていると他の先生も保育室に来て、抱っこして一緒に入ってくれたりします。
そんなこんなで、小規模保育園に比べて保育室に預けるのにすごく時間がかかっています。
小規模保育園のデメリット
①3歳で強制的に転園する必要がある
3歳の壁と言われたりしますね。
小規模保育園を卒園した後、新しく通う保育園を探す必要があります。
普通の認可保育園には0歳~2歳のクラスから在園しているこども達が既にたくさんいて、3歳以上のこどもは小規模保育園では預かってもらえず、小規模保育園を卒園したこども達の行き場を親がみんな心配しています。
でも保育園の激戦区と言われる場所には保育園がどんどん新設されていますし、認可保育園、認可外保育園、インターナショナルスクール、幼稚園など、長男のお友達もほとんどみんな行き場が決まりました。
中にはお母さんが育休中で次の年も仕事を休む予定だったお友達は、なかなか保育園が決まらなかったようです。
それでも卒園までに認可保育園の人数調整があったようで新しく通う保育園が決まっていました。
そして、新しい保育園が決まっても、またこどもの保育園拒否運動が始まってしまいます。
ならし保育が始まり、保育園行きたくない、知らないお友達ばっかりだから、知らない先生だから嫌だと毎朝泣く日々が始まります。
仕事が休みになるわけでもなく、お母さんがいいと泣かれ、預ける親も心苦しくなり大変な時期ですよね。
②在園中にお友達が転園してしまう
長男は小規模保育園に入園した時から仲良しだったお友達が、途中でインターナショナルスクールに通うことになったり、普通の認可保育園に転園することになったりして、仲良しのお友達が順番にいなくなっていきました。
3歳の壁を心配してずっと転園希望を出しているお友達もいたようで、転園してしまいました。
我が家は小規模保育園を気に入っていたので、卒園まで通わせてあげたいと思い、転園を検討しなかったのですが、色んな理由で転園していくお友達もいたので、長男が寂しそうにしている時期もありました。
引っ越しなどもあり、お友達が転園していくのは小規模保育園に限った話ではないのですが、小規模保育園では人数が少ない分、仲良しのお友達がいなくなる寂しさが大きいようです。
③2歳になると年上のお友達がいないので刺激が少ない
今の保育園では0歳から5歳までいるので、0歳から2歳のクラスの子供たちは常に3歳から5歳のクラスのお兄さんお姉さんに憧れながら見ています。
3男は、次男が運動会や生活発表会に向けて保育園で練習している歌や体操など、よく見てよく覚えて
います。
次男も長男が3歳から5歳のクラスにいた時、どんな事をしているのか興味津々で生活発表会の練習や運動会のダンス、体操などを長男と一緒に家で練習していました。
1歳のクラスでも手遊びをしたり歌を歌ったりしているのですが、それとは別にお兄さんお姉さんが毎日練習している歌や体操が気になるようで、その歌を家でもよく覚えて歌っています。
小規模保育園ではなかなか得られない刺激なのかなと思います。
馴染みやすいポイント
小規模保育園に限らず、こどもが保育園を嫌がるポイントとして、4月入所でみんなが一斉に入所してみんなが泣くというのもあると思います。
長男は12月に認可保育園の空きが出て入所できることになりました。
すると4月から保育園に通っているお友達はみんな落ち着いていて楽しそうに遊んでいます。
長男が泣いていると、おもちゃを持って来てくれたり心配して話しかけてくれたりしました。
みんなが楽しそうに過ごしている環境だと、安心して馴染みやすいのかなと思います。
三男は4月入所でしたが、クラスのほとんどが0歳クラスから通っているお友達で、その中に3人新しく入所したので、お友達の大半が落ち着いて楽しそうに過ごしていましたし、一緒に遊ぼうと声をかけてくれたりお手てを繋いでくれたりしました。
その雰囲気に三男は安心したのか、保育園にすんなり馴染むことができました。
仕事に復帰するタイミングで認可保育園に入れなくても、認可外保育園にとりあえず入所して、認可保育園の空きが出るのを待つのもありかなと思います。
認可外保育園に預けて仕事を始めると、保育園入所の優先順位が上がるので入りやすくなる場合が多いようです。
(各市町村によって異なるので皆様がお住まいの市町村でご確認ください)
まとめ
0歳から2歳と3歳から5歳では保育園に求めるものが違うので、少人数でしっかり一人一人を見て、一人一人に色んな経験をさせて色んな能力を発掘、サポートしてくれる小規模保育園はこどもにとっていい環境だと思います。
0歳~2歳の間は小規模保育園でアットホームな雰囲気で保育園に通うという選択肢もありだと思います。
保育園の送り迎えの都合上、兄弟で同じ保育園に通ってほしいので、我が家では長男しか小規模保育園に通いませんでしたが、長男のお友達は妹や弟をぜひ小規模保育園に入れたいということで、兄弟で別の保育園に通っている人も多いです。
希望した保育園に必ず入れるわけではありませんが、保育園を見学して、保育園の雰囲気や先生方の雰囲気をよく見て、こども達が楽しく過ごせる保育園に通えるといいですね。
今回も最後まで読んで頂いてありがとうございました。
また次回配信もお楽しみに。